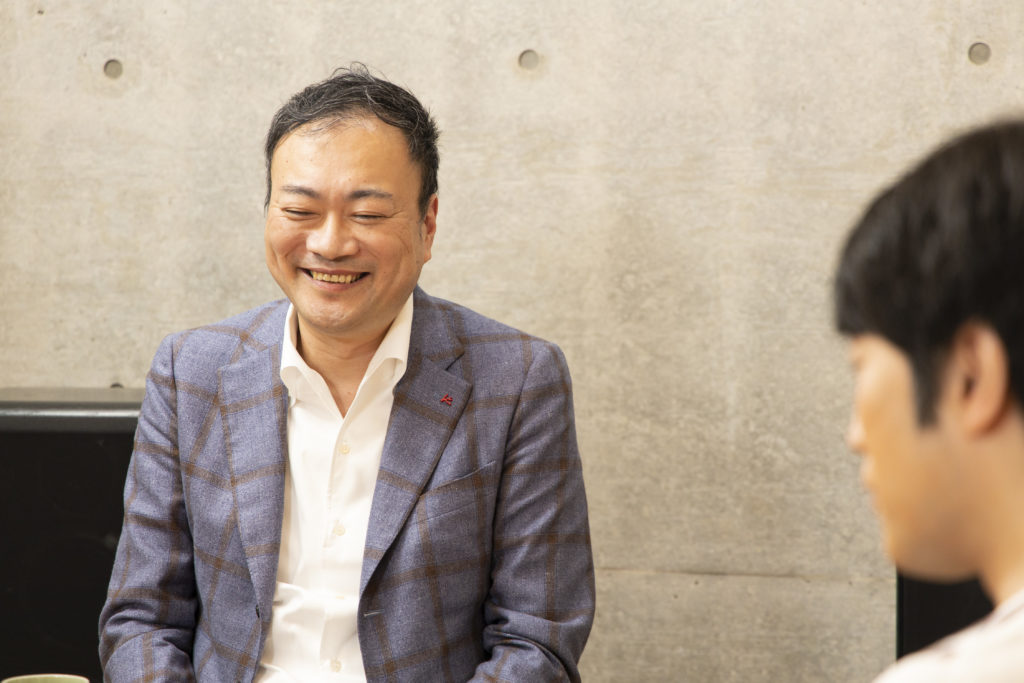バンドネオン奏者・小松亮太の「住まい論」
バンドネオン奏者
小松亮太
一級建築士
住まいのあり方が多様化し、それぞれの価値観、ライフスタイル、またライフステージに合わせて、選択肢は広がり続けています。こうした中、「自分らしい家をつくること」の魅力を、また「自分らしい家で暮らすこと」の価値を、あらためて多くの方に知っていただきたい――そんな思いから、「More Life Lab.」は生まれました。
生き方・暮らし方を自ら定義し、つくり上げようとする人。
その価値観に賛同し、肯定したい。
上質と個性を重んじ、人生を通じてそれを謳歌したいと願う人。
その思いに寄り添い、実現を後押ししたい。
家が人に与えてくれる幸せや可能性を誰よりも信じ、住まいに対するお客さまの思いやこだわりと誰よりも深く向き合ってきた「家づくりのプロ」として。上質かつ自分らしい家で、心満たされる豊かな暮らしを送りたいと考えるすべての方に、家づくりにまつわる知識と教養をお届けします。
「M」の右斜め上に伸びるラインが象徴するのは、「もっと自由に、自分らしく」という、住まいづくりの考え方。左下へ伸びるラインは、光と風のベクトルを表し、自然を取り入れる暮らしの心地良さを連想させます。上下に広がる造形が、「もっと自由に、自分らしく」と望む人の周りに広がる空間の存在を感じさせます。
テラジマアーキテクツは、創業以来60年にわたりデザイン住宅を手がけてきた、住宅専門の設計事務所+工務店です。
お客さまのライフスタイルに合わせたオーダーメイド住宅をつくり上げています。
東京都・神奈川県で家を建てることにご興味のある方は、下記のウェブサイトも併せてご覧ください。
建築家による設計・施工実例を多数ご紹介しています。
https://www.kenchikuka.co.jp/
バンドネオン奏者
一級建築士
毎回特別なゲストを迎え、住まいへのこだわりを語り尽くす対談企画。新しい価値を世に発信するクリエイティブな人々は、自分らしい空間を自らつくり上げることにも長けています。ゲストそれぞれが感じる「豊かな暮らし」「自分らしい住まいづくり」を建築家・深澤彰司がじっくり掘り下げます。今回のゲストは、世界的バンドネオン奏者として長年にわたって日本タンゴ界を牽引し続けている小松亮太さんです。
1973年生まれ。東京都出身。 両親ともタンゴ奏者の家庭で育ち、14歳よりバンドネオンを独習。1998年、ソニーからCD『ブエノスアイレスの夏』でデビュー。世界的なバンドネオン奏者・作曲家として幅広く活躍。2021年に新著の出版を控える。
https://ryotakomatsu.net/
◎新著『タンゴの真実』
発売日:2021年2月予定 出版社:旬報社
◎アルバム「ピアソラの芸術」
発売日:2020年12月9日 発売元:ソニーミュージックレーベルズ
http://www.sonymusic.co.jp/artist/RyotaKomatsu/discography/SICC-40109
◎小松亮太タンゴ五重奏 with 彩吹真央
2020年12月19日・20日 @シアター1010(東京)
https://www.t1010.jp/html/calender/2020/384/index.html
◎小松亮太 カルテット ニューイヤーコンサート
2021年1月17日@タウンニュースホール(神奈川)
https://townnews-entertainment.jp/archives/8457
◎小松亮太 アルゼンチン・タンゴ・コンサートwith 寺井尚子
2021年1月30日(土)
八千代市民会館大ホール(千葉)
https://ryotakomatsu.net/liveinfo/609.html
◎小松亮太&オルケスタ・ティピカ~アルゼンチン・タンゴ・コンサート~
2021年2月19日 @東大和市民会館ハミングホール(東京)
https://www.humming-hall.jp/event/200523.php